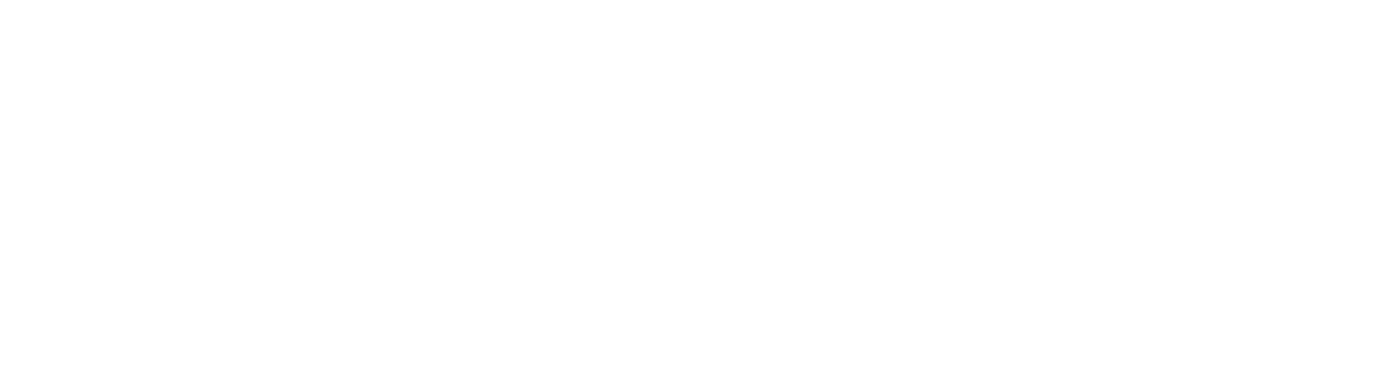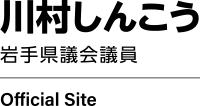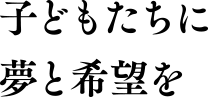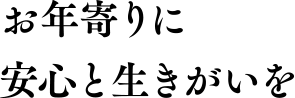NEWS
プロフィール

- 氏名
- 川村 伸浩(かわむらしんこう)
- 出身地
- 岩手県花巻市高松
- 生年月日
- 昭和31年2月19日
- 家族
- 妻・母・子供夫婦・孫3人・犬1匹
- 性格
- 辛抱強い
- 趣味
- 釣り・温泉
- 尊敬する人
- 新渡戸稲造
- 言葉
- 一期一会
- 身長・血液型
- 178cm・A型
〈県議会議員としての主な経歴〉
平成27年9月〜平成29年9月(1期)
農林水産委員会 委員
ふるさと創生・人口減少調査特別委員会 副委員長
東日本大震災津波復興特別委員会 委員
県政調査会幹事
岩手県議会情報公開審査会委員
自由民主クラブ(会派)所属
平成29年9月〜令和1年9月
総務委員会 副委員長
産業振興・働き方改革調査特別委員会 委員長
東日本大震災津波復興特別委員会 委員
自由民主クラブ(会派)所属
自由民主クラブ政策担当
令和1年9月~令和3年9月
商工建設委員会 委員
議会運営委員会 委員
環境問題・地球温暖化対策調査特別委員会 委員
東日本大震災津波復興特別委員会 委員
広聴広報会議 座長
議員定数等検討会議
自由民主党(会派)
令和3年9月~令和5年9月
農林水産委員会 委員長
地球温暖化・エネルギー対策調査特別委員会 委員
東日本大震災津波復興特別委員会 委員
新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会 委員
議会改革推進会議 副座長
議員定数等検討会議
自由民主党(会派)
令和5年9月~
文教委員会 委員
東日本大震災津波復興特別委員会 委員
観光・交通政策調査特別委員会 委員
岩手県監査委員会 委員
自由民主党(会派)
令和7年9月~
商工建設委員会
議会改革推進会議 座長
グローバル化・多文化共生調査特別委員
東日本大震災津波復興特別委員
自由民主党(会派)
〈経歴〉
昭和43年3月 花巻市立矢沢小学校卒業
昭和46年3月 花巻市立矢沢中学校卒業
昭和49年3月 岩手県立黒沢尻工業高等学校
〈職歴〉
- 昭和49年4月〜昭和54年2月
- リコー光学(株)勤務
- 昭和54年3月〜
- 農業
- 平成17年3月31日〜
- 農業生産法人 有限会社あぐりらんど高松 代表取締役
〈各種公職歴等〉
- 平成8年7月〜平成11年7月
- 花巻市農業委員
- 平成10年4月1日〜平成22年4月
- 花巻市認定農業者協議会 会長
(花巻市担い手農業者連絡協議会 会長) - 平成12年6月〜平成16年6月
- 岩手県認定農業者組織連絡協議会 会長
- 平成13年6月〜
- 猿ヶ石北部土地改良区(監事・理事・副理事長)
- 平成14年4月〜
- 花巻市バドミントン協会 会長
〈自由民主党での主な経歴〉
自由民主党岩手県支部連合会 組織運動本部長 令和5年10月~
自由民主党岩手県支部連合会 財務委員長 令和5年1月~
自由民主党岩手県支部連合会 市町村選挙対策室長 令和4年1月~
自由民主党岩手県支部連合会 総務会長 ~令和4年1月
自由民主党岩手県支部連合会 広報委員長 ~令和1年11月
自由民主党花巻市支部 支部長
自由民主党岩手県支部連合会 総務会長 令和7年10月~
〈市議会議員としての主な経歴〉
平成11年4月30日〜平成27年5月29日 花巻市議会議員 (6期)
平成22年8月9日〜平成27年5月29日 花巻市議会 議長
全国市議会議長会 監事
全国市議会議長会
国と地方の協議の場検討特別委員会 副委員長
岩手県市議会議長会 副会長
議会運営委員会 委員長
産業経済常任委員会 委員長
福祉常任委員会 委員
建設常任委員会 委員
悪臭公害対策特別委員会 委員長
花巻空港臨空都市構想推進特別委員会 副委員長
花巻市消防委員会 委員
しんこう8つの目標
1.人口減少への対応
日本の人口減少は大きな社会問題です。特に大きな影響を受けているのが地方です。社会減と自然減、人口減少を少しでも抑える対策に取り組みます。
2.基幹産業である農林水産業の振興
農林水産業の振興を図るために担い手の育成、基盤整備の促進、女性農業者の育成支援、中山間地域の活性化とスマート農業の推進を図ります。
3.商工業の振興
人口減少を迎える中で商工業が持続的に発展し、賑わいと活力の創出、安定的な雇用の確保に取り組みます。地域の産業・雇用を支えている中小企業への支援を図ります。
4.観光立県いわての促進
観光は岩手県の重要な産業です。岩手県の魅力を国内外に積極的に発信し、外国人観光客や教育旅行などを含む多くの観光客が岩手を訪れていただくよう取り組んでまいります。

5.学校教育の充実と人づくり
子供たちの学力向上、運動能力の向上と教育環境の整備を図り、スポーツ・文化・芸術・伝統芸能を担う人材育成に取り組みます。
6.明るく豊かな長寿社会の実現
お年寄りの生きがいと仲間づくりなど安心して暮らしていける環境づくりに取り組みます。
7.若者の雇用創出と安心して
働ける環境づくり
地方ならではのイノベーションによるサービス産業、農林水産業、建設業の生産性の向上など新たな雇用の創出を図ります。新たな成長産業の掘り起こしとILCの実現に向け取り組みます。
8.東日本大震災からの復興
ハード面の復興は進んだものの暮らしの再建、生業の再生、未来のための伝承発信に取り組みます。